教育改善
社会基盤デザイン学科の教育改善システム
本学科では、教育プログラムを継続的に改善していけるよう、図1に示すように、学科の教職員全員を構成員とする「学科会議」を中心に、学習・教育目標、教育手段、教育環境等を点検・検討する「プログラム検討委員会」、および学習・教育目標の達成度等を点検・評価する「点検・評価委員会」を設けて、教育プログラムの点検とその改善を図っています。
そして、図2に示すように、基本的には6年程度を1周期とする教育プログラムの継続的な改善を行っています。すなわち、さまざまなプラン(学習・教育目標、カリキュラムなど)を策定し(Plan)、それを実行に移して(Do)結果を点検し(Check)、さらなる改善を目指して方針や実施体制を再確立する(Action)、といった活動をサイクル的に行っています。実行・点検・改善(Do-Check-Action)の作業は、1年毎の周期で行い、次年度への課題と対策をまとめたアクションプログラムや各科目の内容や評価方法等をまとめたシラバスと組み合わせて、翌年度の取り組みへ反映させています。
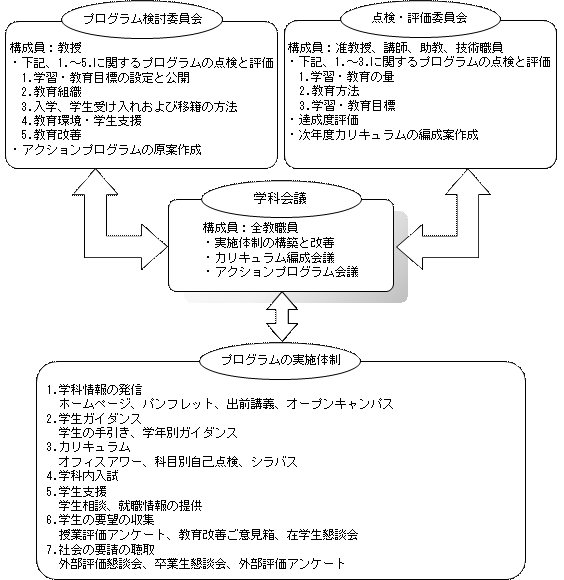
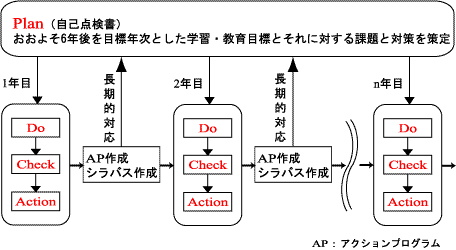
学生による授業評価
各学期の終わりには、学生による授業評価アンケートを実施しています。その授業に意欲的に取り組んだか、担当教員の準備状況は十分であったか、どのような改善を望むか、などを記入してもらいます。その集計結果や個々の具体的な意見をもとに、担当教員は次年度以降の授業の仕方を練り直しています。
教育改善ご意見箱
社会基盤デザイン学科では、教室内に「教育改善ご意見箱」を設置し、授業評価とは別に、授業科目や時期を限らず、社会基盤デザイン学科の教育プログラムに関する意見や要望、質問などを気軽に投稿できるようになっています。「教育改善ご意見箱」に投函された意見等は、学科会議の際に対応を検討し、所定の期間内に何らかの回答(場合によっては行動)を示すようになっています。
教員による授業改善への取り組み
社会基盤デザイン学科の前身である建設工学コースでは、授業等を実施するにあたって、授業の進め方、出席の確認方法、試験の実施方法、単位の認定などの基本的事項を確認しておくために、2006年度に授業実施の覚書を作成しました。この授業実施の覚書は、本学工学部で実施している再試験システムの変更などを考慮して内容を見直すなど(2009年度に改訂)、実状にあわせて改訂を行っています。
また、FD(Faculty Development)の一環として、時期を決めて教員同士が授業を参観し、教員のレベルから授業の内容や方法を順次チェックしていましたが、ほとんどの授業科目の参観を実施し、一定の効果が認められたため、2008年度のアクションプログラム検討会議においてFDに関する新しい取り組みについて検討しました。現在では、毎月開催される教職員による学科会議の際に、FD報告会を実施し、講義の実施方法、講義実施における問題点とその改善方法などを各教員が順に報告し、意見を出し合うことにより教育システムを継続的に改善しています。
